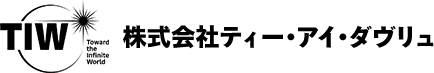特別寄稿
一橋大学大学院 准教授
円谷 昭一
~『政策保有株式の実証分析』概要 ~
コーポレート・ガバナンスの専門家である一橋大学大学院の円谷准教授が、株式持合い分析の決定版とも言える『政策保有株式の実証分析』を発刊しました。株式持合いが発生した歴史的な経緯・変遷、経済効果に関して網羅的に分析を行っています(最後の目次ご参照)。 今回、特に収益性や企業価値向上にポイントを置いて著書のエッセンスについて寄稿を頂いた。
-大量データによる初の実証分析-
持合い株式の売却を迫る機関投資家の声は日に日に増しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとして株式売却を促す諸制度が整備されてきている。一方で、株式持合いによって取引先との関係が維持・強化されると主張する声も小さくない。研究者の間でも株式持合いの評価は一様ではない。ではなぜこれほど長く議論が続けられているのだろうか。
その理由の1つには、株式持合いのメリット・デメリットが不明確であり、さらにはそれらを明らかにするための実証研究が不足していることが挙げられる。しかしながら、2000年の金融商品会計基準の導入によって開示が始まった有価証券に係る情報や2010年から開示が始まった政策保有株式の情報を用いることで、このような困難はかなり克服されてきている。
本書(『政策保有株式の実証分析』)では、政策保有株式データを用いることで、これまで日本では行われてこなかった株式持合いに関する本格的な実証研究を実施した。その分析手法も出来る限りシンプルなものを採用することで、より多くの読者層に結果を訴求できるように工夫している。
企業集団と相互保険システム説
現在の政策保有株式の歴史的な源流は戦前の財閥にまで遡るが、終戦による財閥解体政策によっていったんは株式持合いの歴史が途切れることになる。しかしながら、財閥家族や財閥本社から放出された大量の株式をめぐって個人投機家(グリーンメーラー)や外資による買収の危険性が高まり、機関投資家が存在しなかった当時では、企業間の持合いによる買収防止を図るしかなかった。こうして、戦後に新たな形での株式持合いが進展する。その持合いの軸となったのがいわゆる六大企業集団(三菱、三井、住友、芙蓉、三和、一勧)であった。
六大企業集団については実証研究も含めて多くの学術研究が蓄積されている。そうした研究の結果、企業集団の構成企業の利益率は(非構成企業と比べて)相対的に低いものの、利益率の安定性が高いことが明らかにされている。株式持合いの効果として、この「相互保険システム説」が通説となっている。しかしながら、高度経済成長の終焉後はこの相互保険システムが成り立たなくなっているという研究報告がなされており、その後のバブル崩壊によって企業集団自体がほぼ消滅したため、株式持合いに関する実証分析は実質的に途絶えてしまった。一方で持合い株式の残滓である政策保有株式を一部の日本企業は依然として多量に保有しているのも事実である。よって、政策保有株式の多寡によって企業の会計特性がどのように変化するかについてあらためて分析を実施する必要がある。
本書では最新のデータを用いながら、利益率、利益率の変動性、売上高・総資産の成長性という視点で実証分析を行った。
政策保有株式の現状
本書では、有価証券報告書で記載されている政策保有株式データを用いて主な分析を行っている。まず上場会社が保有している政策保有株式の状況を明らかにすると、政策保有株式は上場会社全体に広く均一的に保有されているわけではなく、一部の企業が多くの株式を保有していることが分かる(本書の図表7-8)。他方で、まったく保有していない企業、ほとんど保有していない企業も少なくないのが現状である。また、時系列で保有量の推移を見ると、株式持合いは徐々に解消に向かっているものの、政策保有株式の開示の開始やコーポレートガバナンス・コードの導入を機にして劇的に低下しているという事実は観察されなかった。各種アンケート調査からも、銀行との株式持合いは継続する、相互持合いの場合には解消しない、といった事業会社の回答も得られており、こうした核となる株式持合いはいまだ継続していることが分かる。
政策保有株式と会計数値の関係
第1の検証は、政策保有株式の多寡と会計数値との関係である。相互保険システム説では、株式持合い関係にある企業の利益率は低いものの、利益率の安定性や成長性の面でメリットを享受していた。ただし、これらの研究は1970~80年代に行われたものが多く、現在の政策保有株式においても同様の傾向が見られるかどうかをノンパラメトリカルな統計手法によって検証した。
利益率、利益率の安定性、売上高・総資産の成長性のそれぞれの検証の結果、大きく2つの点が明らかとなった。まず、利益率に関しては、政策保有株式を多く持つ企業の利益率が低いことが明らかとなった。東証1部上場会社にサンプルを限定するなど、いくつかの追加分析も実施したが同様の結果が得られている。もう1つの明らかとなった点は、利益率の安定性と売上高・総資産の成長性の特徴である。政策保有株式を持っている企業群に限定した場合には、政策保有株式を多く持っている企業の利益率の安定性や売上高・総資産の安定性は、それほど株式を保有していない企業と比べて異なっているという結果は得られなかった。
つまり、政策保有株式を多く持っている企業では利益率の安定性や成長性といったメリットを享受することなく、ただ低利益率であるということが観察された。ただし、これらの検証では、新興企業と成熟企業という企業特性の違いが結果に影響を与えている可能性が排除できなかった。そこで株式をある期に売却したサンプルを抽出し、同一サンプルによる時系列比較によって、売却の前後で会計数値が変化しているかどうかを検証した。
株式売却前後の会計数値の変化
第2の検証では、その他有価証券をある期に売却した企業をサンプルとして、売却の前後で会計数値が変化しているかどうか、とりわけ会計数値が売却後に悪化しているかどうかを明らかにした。その結果、利益率、利益率の安定性および売上高・総資産の成長性ともに、売却後にそれらが悪下するという結果は観察されなかった。利益率や成長性に関する結果の一部では、株式売却によって利益率と成長性の向上が観察された。これらの結果の解釈として、株式売却によってそれまで拘束的であった取引関係をより柔軟に築けるようになったことに起因している可能性が指摘できる。
これらの結果の含意は、株式持合いによって会計数値を変化させるだけの取引関係の維持・強化はなされていないことを意味する。とりわけ、利益率という視点から見た場合、株式持合いは利益率の向上に寄与していないばかりか、持合いが強固な企業では逆に低い利益率に甘んじているという結果となった。もちろん、一部企業では株式持合いによって取引関係の維持・強化がなされ、それが利益率の向上につながっている企業もあると思われる。しかしながら、全上場会社のデータを用いた検証の結果からは、株式持合いが強固な企業の利益率が平均的に見れば低いという結果となった。
では、なぜ利益率が低いのか。株式持合いによって、買収の脅威から解放されるがゆえに経営者の企業家精神が薄れ、持合い相手先との調整が過剰であるがゆえに経営が近視眼化し、中長期視点での経営改善から目を背けているのではないかと本書では考える。つまり、まだ株式買占めの脅威が存在した頃には、株式持合いは買占めの脅威という矢玉から身を守るための鎧としての役目を果たしたが、買占めの脅威が去った今では自らの手足を縛る重し、経営改善の足枷となってはいると解釈できる。これが低い利益率へとつながっているのである。
政策保有株式の売却要因
第3の検証は政策保有株式の売却要因に関するものである。第2の検証において、株式の売却前後において会計数値の変化が生じていないことが明らかとなった。この結果は、政策保有株式を持つことによって会計数値が向上することはない、という結果と整合的である。近年、コーポレートガバナンス・コードの導入・改訂や、議決権行使助言会社ISSやGlass Lewisの行使助言方針の改訂の中で、政策保有株式については厳しい視線が向けられている。こうした状況の中で、株式を売却しようとする動きが一部の企業の中で出てきている。
では、どうような企業が、どのような保有銘柄を売却しているのであろうか。これを多変量解析(プロビット分析)に明らかにした。検証の結果、以下の点が明らかとなった。
第1に、政策保有株式の売却は、保有企業の財政状態、経営成績、株式保有リスクなどによって決定される可能性がある。こうした点は保有企業の内的要因が政策保有株式の売却を促していることを示唆している。
第2に、先行研究で指摘されているような、安定株主構築による買収の脅威の低減といったエントレンチメント動機に基づいて政策保有株式の売却が行われている、という強い証拠は得られなかった。これは高度経済成長期およびバブル経済期に株式持合いの目的が当初の株式買占め防止から変質してきたという筆者の考えを裏付けるものである。
第3に、投資先との関係性と政策保有株式の売却とに関連がある可能性がある。具体的には、事業会社間での相互持合い株式やメインバンク株式が売却される可能性が低くなる。換言するならば、片持ち株式やメインバンク以外の銀行株式については、資本市場のモニタリング(カバレッジしているアナリスト数や格付けの取得有無)によって株式売却が促進されることを示唆している。
今後は、相互持合い株式やメインバンク株式といったような、企業にとって保有継続意思が強い株式の売却をどのように促していくかが、資本市場および基準策定主体(金融庁や東京証券取引所)にとっては重要な論点となると思われる。
企業の安定株主の実態
ここまでの一連の検証は、企業が“保有している株式”に関する検証であった。では、“保有されている株式”の現状はどのようになっているのであろうか。保有されている株式とは、言い換えるならば安定株主のことを意味する。安定株主の一部が法人による持合い株式である。企業の安定株主比率は現行の開示情報からは知ることはできず、正確な状況は分からない。
そこで、企業の安定株主比率は実際にどの程度なのかを明らかにするべく企業アンケート調査を実施した。アンケート調査結果の要点は大きく3つである。
まず、安定株主比率の意識に関しては、「意識している」64.6%、「意識していない」11.2%、「どちらとも言えない」23.5%となった。多くの企業が安定株主比率は意識していると回答しているが、意識していない、どちらとも言えないという回答も少なくない。次に、どのような株主を安定株主と考えているかについては、金融機関持株、政策保有株式(金融機関除く)を安定株主と考えている企業は約半数にとどまる。従業員持株会がもっとも回答が多く、長期保有の機関投資家も安定株主と考えられている。安定株主の中で金融機関持株や政策保有株式の存在感は突出して高いというわけではなく、自社の安定株主と考える株主属性は、各社によって様々である。最後に、現状の安定株主比率と目標とする安定株主比率を質問した。まず現状の安定株主比率は「20%未満」から「60%以上」まで企業ごとにバラつきがある。平均値を試算すると44.4%となった。続いて安定株主比率の目標については、全体の61.5%が「特に目標はない」と回答しており、「50%台」12.8%、「60%以上」8.0%と続いている。
設問1・2の結果と総合すると、「安定株主比率を意識してはいるが、具体的な目標値は定めていない。安定株主は金融機関・事業会社による政策保有株式だけにとどまらない」という実態が浮かび上がってくる。マスコミ等では安定株主=持合い株式と考えられることも少なくないが、安定株主の中では持合い株式の存在感は決して高いわけではなく、従業員やファン株主、一部の機関投資家も安定株主と企業は考えているようである。現在、政策保有株式の売却が進められているが、売却された株式をどのような株主主体が取得していくのかについては、引き続き注意が必要である。
企業と資本市場への提言
一連の分析から分かることは、政策保有株式は企業の会計数値の向上に寄与しておらず、逆に保有企業の利益率が低いことがわかった。つまり、企業側が保有理由としている「取引関係の維持・強化」は、会計数値という点からは観察することができなかった。
この検証を踏まえ、企業と資本市場に次のような提言をしたい。まず企業に対しては、法人同士の株式持合いに依存しない安定株主の確保の必要性である。機関投資家や個人投資家も厚みを増し、こうした株主層を自社の安定株主とすればよいのである。経営の安定性をどうしても確保したいのであれば、種類株式の活用や非公開化も視野にいれてよいであろう。もちろん、株式を買い増すという選択肢もある。本当に自社にとって大切な相手なのであればさらに資本を投下すればよい。友好的なM&Aによって国内の事業再編を進め、そしてグローバル企業と伍していく。これまで長期にわたって安定株主であったという関係を逆に利用し、企業再編の呼び水とすることもできるであろう。
次に、機関投資家への提言である。日本の機関投資家は政策保有に反対しているが、当該企業の株式を売却したり株主提案したりといった行動はとらない。その意味で、“冷たい資本”とも言える。機関投資家が置かれている状況はもちろん理解できるが、ただし、企業に汗をかいてもらうことを求めるのであれば、自分もまた汗をかくという決断が必要であろう。
政策保有株式の実証分析 失われる株式持合いの経済的効果
円谷昭一著 日本経済新聞出版 (2020/6/20刊) 5,500円(税込)
序章 本書の問題意識と用語の定義
第Ⅰ部 政策保有株式(株式持合い)の成立
第1章 株式の集中化とその漂流
第2章 株式持合いの本格化
第3章 企業集団の形成と株式持合い
第4章 株式持合いの変質とバブル崩壊
第5章 コーポレート・ガバナンスと政策保有株式の時代
第Ⅱ部 政策保有株式の経済効果の実証分析
第6章 株式持合いの効果と経済的影響
第7章 実証分析で用いるデータの特徴
第8章 政策保有株式と会計数値の関係
第9章 株式売却前後の会計数値の比較
第10章 政策保有株式の売却行動の決定要因
第11章 日本企業の安定株主の実態
第12章 議決権の価値算出の一試案
終章 なぜ、持合いを続けるのか
円谷昭一(つむらや・しょういち)
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
2001年、一橋大学商学部卒業。2006年、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士(商学)。埼玉大学経済学部専任講師、准教授を経て、2011年より現職。2019年、韓国外国語大学客員教員。日本IR協議会客員研究員(2007年~)。日本IR学会理事。
2013年、経済産業省「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築を考える~」委員、経済産業省「企業会計とディスクロージャーの合理化に向けた調査研究」委員、2017年、りそなアセットマネジメント「責任投資検証会議」メンバー。専門は、ディスクロージャー、IR(Investor Relations)、コーポレート・ガバナンス研究。