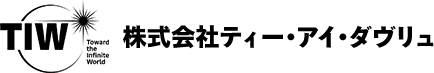■昨年の貿易収支は20兆円の赤字
■貿易赤字は家計簿と似ている
■輸出企業の現地生産は歓迎すべき動き
■エネルギー自給率は高めたい
■日本国のFIREに近づいていくかも
(本文)
■昨年の貿易収支は20兆円の赤字
昨年分の貿易統計が発表され、貿易収支が20兆円という巨額の赤字になった事が話題となっているようだ。かつて日本は巨額の貿易収支黒字を続け、欧米諸国との貿易摩擦が激しかった事を記憶している筆者にとっては、隔世の感がある。
貿易収支は、長期的に黒字が減る傾向にあり、最近では貿易収支は概ねゼロ近辺で推移していた。その主因は輸出企業が現地生産化を推進している事であるが、この点については後述する。途上国の技術進歩によって、製品類の輸入が増えている事も重要な要因である。
昨年の特殊要因としては、原油価格等が高騰して支払い金額が激増したことが重要だろう。半導体等の部品が不足して生産が滞った品目があった事も要因かも知れない。
ちなみに、円安で輸入金額が膨れ上がった事は確かだが、円高で輸出金額も膨れ上がっているので、影響は限定的なはずだ。輸出の方が円建て取引の比率が若干高いが、気にするほどの差では無いようだ。
ここで重要なことは、貿易収支が赤字になっても、特に憂いる必要は無い、ということだ。赤字という単語は否定的な言葉だが、それに惑わされないように気をつけたい。
■貿易赤字は家計簿と似ている
家計簿の赤字は、貧しい家計であれば問題であるが、豊かな家計であれば、それほど問題とはならない場合も多いはずだ。大いに楽しんだ結果として家計簿
が赤字になっても、豊かな人生を送れたのだから問題ないだろう。現役時代に十分老後資金を蓄えた高齢者は老後の家計簿が赤字になっても何も問題ではなかろう。
そして、貿易収支は家計簿と似ている。自分が働いて相手が楽しんで、対価を受け取るのが輸出であり家計簿の収入である。相手が働いて自分が楽しんで、対価を支払うのが輸入であり家計簿の支出である。
そして、日本国は過去に貿易黒字で巨額の外貨を蓄えているわけで、「老後資金を蓄えた豊かな高齢者の家計が赤字になっている」といった状況なので、特に問題は無いわけだ。
失業して収入が無いから家計簿が赤字だ、というのは問題であるし、日本製品が売れずに国内に失業者が大勢いる、という貿易赤字であれば問題だが、国内は労働力不足なので、その面でも問題は無いだろう。
安心材料はまだある。家計簿には利子配当等も記載されるから、正確に言えば貿易収支に加えて所得収支(利子配当等)なども加えた経常収支の方が家計簿に似ている。そして、日本は利子配当等の収入が巨額なので、経常収支は黒字なのである。
■輸出企業の現地生産は歓迎すべき動き
輸出企業は、現地生産を志向しているようだ。円安だからといって輸出を増やすために工場を建てると、将来円高になった時に工場が無駄になってしまうので、はじめから売れる所で作ることにして、工場を現地に作る、というわけだ。
もうひとつ、人口が減っていく日本よりも人口が増えていく海外市場をターゲットとし、労働者も少子高齢化で労働力不足となっていく事が見込まれる日本人よりも人口が増えていく地域の人を雇いたい、という事もありそうだ。
現地生産化によって輸出が減り、貿易収支が赤字になるかも知れないが、それは上記のように大した問題ではない。
一方で、現地子会社から親会社に配当が支払われるとすれば、配当利回りは米国債の利回りより高いと期待される。現地生産のための海外子会社設立は、日本の対外純資産の有効な活用方法なのだ。
加えて、現地子会社から親会社に特許権使用料等々が支払われる場合も多いので、その意味でも日本が海外から稼ぐことに大いに貢献するわけだ。
■エネルギー自給率は高めたい
昨年は、エネルギー価格が高騰した事で貿易赤字が拡大したが、エネルギー価格は上がったり下がったりするので、それは仕方ないだろう。問題は、そもそもエネルギーの自給率が低く、しかも原油の輸入を中東に頼りすぎていることだ。
原子力発電については本稿では論じないが、再生可能エネルギーの活用を進めたり、海底からメタンハイドレードを掘り出したり、エネルギーの自給率を高めることが望ましい。
■日本国のFIREに近づいていくかも
極端な話をすれば、日本は少子高齢化によって「現役世代は全員が高齢者を介護しているので、製造業が存在しない」国になるかも知れない。さすがにそれでは潤沢な対外資産もすぐに枯渇してしまうだろうが、「現役世代がほぼ全員で高齢者を介護しているので、輸出品を作る余裕が無い」という国にはなるかも知れない。給料を受け取らない家計簿になるわけで、日本国がFIREする、というわけだ。
本当にそうなるとは思われないが、それに近づいていく事は考えられるだろう。
本稿は以上である。なお、本稿はわかりやすさを優先しているため、細部が厳密ではない場合があり得る。
(1月23日付レポートより転載)