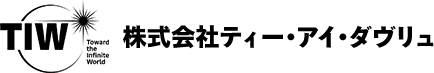中国の日本化、つまりは日本の失われた30年の追随、がいよいよ始まったようだ。
不動産大手が次々と破綻の危機に瀕している。恒大集団に続き、碧桂園が米ドル債の利息を払えず、2023年1-6月期の最終損益が500億元(約1兆円)程度の赤字に転落したと発表した。中国メディアは同社が近く債務再編に乗り出すと報じている。
中国の不動産調査機関によると2022年の不動産販売額で碧桂園は1位(約7兆1000億円)であった(因みに恒大集団は30位、約8600億円)。株価は既にピークに比べて90%超の下落となっている。
また、かねて話題になっていた遠洋集団も8月22日、人民元債の償還が困難になり期限の延長などを提案すると発表した。
更には、中国最大級のノンバンクである中植企業集団では金融商品の不払いが発生した。
恒大集団だけで50兆円近くの負債(約13兆円の債務超過)があるが、それをどのようにして解消していくのか今のところ道筋は見えない。政府が主導しなければ解決へ向かわないと思われるが、一向にその気配がない。その間に不動産全体の傷が深くなってきているというのが現状である。
米ゴールドマンサックスは中国の地方政府が抱える負債規模を94兆元(1880兆円)と試算している。また、IMFは融資平台の負債総額を66兆元(1300兆円超)と試算している。
中国ではGDPに占める不動産関連の比率が約3割といわれてきた。それが崩落過程を歩み始めたわけだから、経済への影響は計り知れない。これに人口減少、米中のデカップリングが加わるわけで、経済低迷は勿論のこと、下手をする習近平の独裁体制が大きく揺らぐ可能性も否定できない。
さて、不動産バブルの崩壊といえば、先輩の日本のバブル崩壊を思い出さずにはいられない。
日本も1980年代までは土地神話が存在した。実際、土地価格は戦後、オイルショック時を除き基本的には右肩上がりを続けた。
80年代後半になると資金が実体経済よりも不動産や株式により多く流れるようになり、東京湾再開発などの大型案件が目白押しで土地価格の上昇が加速していった。1986年には東京都の商業地の地価は前年比75%上昇、1987年は更に37%上昇と2年間で2.4倍と正にバブルの様相を呈した。商業用だけではない、マンション価格も暴騰し1億円が当たり前となった。また、小金井カントリー倶楽部の会員権も4億円を超える価格がついた。
当時、山手線の内側の土地の値段で米国全土が買えるという試算が話題になった。
しかし、山高ければ谷深しである。流石に政府・日銀もこのままでは大変なことになると、引き締めに入った。
1990年の総量規制、その前年から始まった公定歩合の引き上げは2.5%から6.0%まで急上昇、その後地価税を始めとした課税強化で、流石に不動の土地神話も崩れ、地価は暴落した。日本は原則土地担保の銀行融資である。銀行はこの地価の暴落をもろに食らった。住専もまたしかり。
最初の住専処理でもたついたこともあり、銀行の不良債権処理が遅れ傷口が広がった。1997年から拓銀、長銀、日債銀が相次いで破綻した。それまで、誰もが都市銀行や長信銀が潰れるなど夢にも思っていなかったのである。
日本の土地資産(価格)は1990年から2002年の間に約1000兆円失われたといわれている。
日本の金融機関の不良債権はピークで約200兆円、最終的に損失は約100兆円とみられている。
こうしたことが中国でこれから起こる可能性が高いと見ている。
単純な試算をしてみよう。1990年の日本の名目GDPは472兆円、1000兆円の地価の下落は凡そ2.1倍である。中国の2022年の名目GDPは2400兆円、その2.1倍は5000兆円、今後これだけの土地価格の下落が見込まれるのである。
今、問題が表面化しているのは土地開発のデベロッパーであるが、次に来るのが金融機関、そして地方政府の順になるのではないか。中国共産党が処理に本格的に動くか、手をこまぬいて見ているのか分からないが、そう遠くない時期に地獄の窯の蓋が開くであろう。
中国経済は今後どのような道筋を辿るのか。1つは日本型が考えられる。日本はバブル崩壊が始まった1991年の名目GDPが495兆円、その後25年間542兆円を上限にほぼ横ばいが続いた。
中国の名目GDPは1989年を起点に2019年までの30年間年率14.5%の成長を遂げ、世界第2の経済大国になった。それが今後数十年間にわたり基本的にゼロ成長になるのである。
もう一つは、急落型である。政府が有効的な対策を行えず、一気に債務問題が爆発した場合一時的には大変な衝撃を世界経済、そして日本経済は受ける可能性がある。
更に大きな懸念は、中国の経済が落ち込み、その結果として習近平の共産党統治体制が揺らげば、台湾侵攻の可能性が高まるということである。台湾侵攻の障壁は米国太平洋艦隊だと見られているが、米軍との台湾をめぐる戦いの帰趨は分からない。
しかし、台湾独自の反撃への手段は何もないのだろうか。最近面白い話を聞いた。台湾の中国に対する唯一、最大の反撃は、ミサイルによる三峡ダムの破壊であるという。もし、攻撃が成功すれば三峡ダムの流域およそ4億人に大きな被害が及ぶ可能性があるといわれる。電力も広範囲にストップする。
いずれにしても中国の台湾の武力侵攻は、中国としても極力避けたいと考えているであろう。しかし、日本の失われた30年をなぞりはじめた中国はこれから苦難の時代を迎える。今の政策を続けて行く限り習近平政権として台湾統一に活路を求める可能性が高まる。そうした状況に少しずつ近づいている。
さて、お先真っ暗な物語を披露してきたが、日本の株式市場は予想される中国経済・政治外交、軍事の先行きから悲観的に見ざるを得ないのか。一般的にはそうかもしれない。
しかし、朝鮮戦争(1950年6月~1953年7月)の時は特需に沸き日本株は上昇した。開戦の年、1950年9月に110円で日経平均(当時は東証修正平均株価)は算出を始め1953年2月に474円に達した。
勿論、今回中国の台湾侵攻があった場合、朝鮮戦争の時のように日本の株価が大幅に上昇すると考えるのはあまりに楽観すぎるであろう。朝鮮戦争当時とは何もかもが違う。開戦当初は当然だがショック安が考えられる。しかし、カギを握るのはあくまでも勝敗の行方である。
台湾侵攻が無く中国経済のバブル崩壊だけであれば、どうなるだろうか。中国の経済が日本型の停滞になるとすれば、成長はしなくとも世界第二位の経済規模は維持するとすれば、中国に成長のエンジン役を期待することはできないが、影響は限定的になるかもしれない。急落型は押し並べて相当程度の影響は被るであろうが、中国依存の大小がモノを言うかもしれない。
もう一つ忘れてならないのは需給である。現在、中国から海外マネーの流失が加速しているようだ。8月は香港市場で既に1兆円の株式の売り越しとなっている(24日現在)。
香港ハンセン指数は8月に入り連日のように下落を続け、一時今年の最安値を付け、18000を割った。2018年1月の高値33154から今月安値の17618(終値ベース)まで46.9%の下落である。
日経平均株価の1989年大納会の38915円から2009年3月の7054円の後を追うということになるとすれば、高値から80%以上下落するかもしれない。まだまだ、下落の余地は大きい。そのような株式市場に資金を置いておく投資家は、特に海外投資家はいないだろう。また、バイデン政権は対中投資規制の大統領令を発表している。今後中国への投資は大幅に縮小するであろうし、既存の資金の流失も続こう。否、国内の富裕層の資金も逃避が始まっているといわれている。強化された反スパイ法の制定がそうした動きを加速させているようだ。
考えなければいけないのはこの中国へ投資されなかった、そして中国から流失した資金の行方である。日本にどのくらい来るのか。日本経済のデフレ脱却、生産性の向上、金融正常化、株式市場活性化などがどの程度進むのか。そこにかかっている。
8月30日付レポートより転載