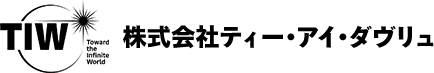アナリストコラム一覧
アナリストの知識や経済・業界動向、活動の中で感じた問題意識など幅広い視野でとらえた情報を不定期に『アナリストコラム』を通じてお客様にお届けいたします。
-
2022/09/06主要中央銀行の利上げラッシュから、FOMC通過までは下押し圧力の強い展開が続く -藤根靖昊-先週も米国株式市場には利上げに対する懸念による暗雲が立ち込めていました。 30日発表の7月の雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が1123.9万件と、34.2万件が上方修正された前月データから19.9万件増加しました(市場予測は1030万件)。求人件数は失業者の2倍を上回る水準にあり、労働需給は依然として逼迫感が残ります。同日発表のコンファレ...
-
2022/08/309月FOMCでは利上げ幅よりドットチャートに注目 -藤根靖昊-注目された26日のジャクソンホール会議におけるパウエル議長の講演は8分間の短いメッセージに“楽観論”への牽制が込められた内容でした。「物価の安定を回復するには引き締め的な政策姿勢をしばらく維持する必要がありそうだ」、「歴史は金融緩和を強く戒めている」、と。しかし、一方で「ある時点で利上げペースを緩めることが適切となる可能性がある」とも述べており、全体としては...
-
2022/08/239月FOMCで0.75%利上げを織り込む展開も、利上げにより転換点を迎える -藤根靖昊-先週も米経済の減速を裏付ける経済指標の発表が多かったようです。7月の米住宅着工件数(16日)は前月の改定値から▲9.6%減となり1年5カ月ぶりの低水準を記録しました。7月の米小売売上高(17日)は市場予想(+0.1%)を下回り前月比横ばいにとどまりました。週次の住宅ローン申請件数(17日:12日までの1週間・総合指数)は2000年以来の低水準を記録したようで...
-
2022/08/16株式市場は経済減速よりも金利低下をポジティブと見るのか? -藤根靖昊-10日発表の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比+8.5%と6月(+9.1%)から低下するとともに市場予想(+8.7%)も下回りました。11日発表の米卸売物価指数(PPI)もまた季節調整済み前月比で▲0.5%となりプラスを見込んでいた市場予想(+0.2%)を大きく下回りました。また、全米自動車協会が発表した11日時点のガソリン価格(全米平均)は3.99ドル...
-
2022/08/09米利上げに対する緩和的見方は後退 -藤根靖昊-ペロシ米下院議長の訪台による瞬間的な緊迫状態から市場は回復しつつあるようです。しかしながら、台湾周辺の緊張は以前よりも確実に増したことはリスク量の増加として認識しておく必要があると考えます。 3日発表の米ISM非製造業景況指数(7月)は低下を見込んでいた市場予想に反して56.7と前月比1.4ポイントのプラスとなりました。さらに5日発表の米雇用統計(7月)に...
-
2022/08/02ペロシ訪台から市場緊迫、中国不動産問題も深刻化 -藤根靖昊-7月26-27日の米連邦公開市場委員会(FOMC)において、事前の市場予想通り0.75%の利上げが行われました。パウエル議長が「金融政策のスタンスがさらに引き締まるにつれて、引き上げペースを緩めることが適切になる可能性が高い」と述べたことから、市場では引き上げペースが緩やかになるとの見通しが強まり、27~29日の3日間合計でダウ平均は1,083ドルの大幅上昇...
-
2022/07/29中国経済の失速はリスクと同時にチャンスかも –客員エコノミスト -塚崎公義 –■中国経済が失速するリスクが懸念される ■中国経済が失速すれば対中輸出減少などの悪影響 ■中国経済が失速すれば資源価格が安定 ■世界的なインフレ懸念の後退は金融市場にもプラス ■長期的なメリットも大きいかも (本文) ■中国経済が失速するリスクが懸念される 中国経済が失速するリスクが懸念されている。筆者が注目しているのは、不動産バブルの崩壊、新...
-
2022/07/12美しい国・日本の終わり -藤根靖昊-経済指標の悪化を受けて米長期金利(10年国債利回り)は6日に2.74%まで低下しました。6日に公表されたFOMC議事要旨において利上げに強い姿勢を滲ませる内容でしたが、景気後退よりもインフレの悪影響をFRBが優先することで金利上昇に歯止めがかかったと市場では捉えられたようです。先週の米国株式市場においては金利に対して敏感なハイテク株の上昇が目立ち、ナスダック...
-
2022/07/05米金利低下による買戻しは一時的とみる -藤根靖昊-先週発表された米国経済指標はいずれも景気減速を示す内容であったことから、株価下落が進みましたが、週末にかけて米長期金利が大幅に低下したことから株の買戻しが生じています。 先週の主な発表は次の通りです。 6月28日発表のコンファレンスボード消費者信頼感指数(6月)は98.7と前月比▲4.5ポイント低下、6カ月先を見通す「期待指数」は▲7.3ポイント減の66...
-
2022/06/28インフレと景気減速の狭間で株価は揺れる -藤根靖昊-27日に主要7カ国首脳会議(G7サミット)において、ロシア産石油の価格に上限を設ける制裁の導入で合意しました。欧米が行ったロシア産石油の輸入停止処置は、原油高を引き起こし、中国・インドや新興国が購入を止めなかったことからロシアへの制裁効果は限定的なものに留まりました。中国の5月の原油輸入量はロシア産が最大となっています。 今回の制裁はロシアの戦費調達を遮断...
-
2022/06/21日経平均株価は米国金利上昇を加味すれば既にコロナ前の水準 -藤根靖昊-先週は経済指標発表をはじめとして冴えないニュースが続きました。NYダウは週間で1,504ドル下落し3万ドルを割り込み、日経平均株価は1,861円安となり26,000円割れとなりました。発表等を時系列で紹介すると次の通りです。 14日:米生産者物価指数(5月)前年同月比▲10.8%。ロシア国営ガスプロムが「ノルドストリーム」向け供給の40%減を発表。 15...
-
2022/06/14高まりつつあるスタグレーションの足音 -藤根靖昊-8日から週末を挟んで13日までの4日間のNYダウの下落幅は2,663.4ドルにも達しました。米小売大手の過剰在庫、インテルの業績悪化懸念、クレディスイスの赤字転落、ECBの7月利上げ発表(9日)など世界景気の下押し懸念が強まり、市場センチメントが悪化している中で、10日発表の米消費者物価指数(CPI・5月)が追い打ちをかけた格好になりました。CPIは前年同月...
-
2022/06/07ロシア・ウクライナ戦争の現在位置の認識について -藤根靖昊-ロシア・ウクライナの戦闘に関しては、5月以降はロシアの劣勢を伝える報道が減少し、むしろロシア優位に大きく傾いているように見受けられます。株式市場に回復傾向が表れつつあるのは、米国利上げがひとまず織り込まれたことが主因であるものの、底流に戦争終結の兆しを市場が感じ取っているのではないかと推察されます。 5月31日の日経朝刊「The Economist“ロシア...
-
2022/05/31米国株式市場の急反発もまだ混沌のボックス圏 -藤根靖昊-前々週(5月16-20日週)まで8週連続の下落となったNYダウは20日から27日まで6日連続上昇しました。この間の上げ幅は1,959ドルにも達しました。この背景にはFRBの「タカ派」姿勢が後退したと市場が捉えたことが要因のようです。 20日にセントルイス連銀のブラード総裁が「インフレ期待が制御できれば23-24年に利下げできると」と発言。23日にはアトラン...
-
2022/05/24中国との緊張高まりを中期的に警戒 -藤根靖昊-バイデン大統領が来日し、23日に岸田総理と首脳会談を行いました。会談後に日米首脳共同声明が発せられ、「自由で開かれた国際秩序の強化」として、ロシアによるウクライナ侵略への非難と制裁継続をはじめ、中国の軍備増強等に対する牽制が声明に込められました。また、バイデン大統領は、記者会見において台湾有事の際には米国が軍事的に関与することを明言いたしました。また、バイデ...
-
2022/05/17ロシアを取り巻く緊張が緩和されない限り、日経平均の28,000円超えは難しい -藤根靖昊-決算発表が一巡した13日時点の22年度のコンセンサス予想EPSは、決算発表前の4月1日時点を1.6%下回りました。下回ったとはいえ比較的高水準が維持された状態です。23年度(来期)に関しては4月1日時点の水準を若干ですが上回っています。22年度業績は原材料高などインフレの影響から伸び悩むものの、23年度には成長軌道に回復するという予想になっています。しかし、...
-
2022/05/10株価の乱高下はまだまだ続く -藤根靖昊-9日にロシアの「ドイツ戦勝記念日」においてプーチン大統領は従前通り正当性を主張する講演を行いましたが、一部の観測に出ていた「戦争状態の宣言」は行いませんでした。懸念された戦線拡大には至らなかったものの、今後のロシアの軍事作戦についての不透明感は増したようにも思われます。 ロシアに対する経済制裁の強化やウクライナへの武器供与拡大から、ロシアを追い込むことは、...
-
2022/04/08株価のファンダメンタルズは不安が山積 –客員エコノミスト 〜塚崎公義 教授 –■株価はウクライナ停戦を見越して戻ったが・・・ ■タイムラグを伴ってインフレ率がさらに上昇か ■世界経済の分断でグローバル化のメリットが縮小 ■脱炭素化の動きが化石燃料の価格高騰を招く恐れも ■中国経済を巡る懸念が需要面、供給面いずれにも存在 (本文) ■株価はウクライナ停戦を見越して戻ったが・・・ 年初来大きく下げていた株価は、かなり持ち直し...
-
2022/01/07来年は中国経済の急減速リスクに要注目 –客員エコノミスト 〜塚崎公義 教授 –■景気は新型コロナの沈静化で回復中 ■新型コロナの第6波への過度な懸念は不要 ■米国のインフレと金融引締めへの懸念は小 ■中国経済の急減速リスクには要注目 (本文) ■景気は新型コロナの沈静化で回復中 新型コロナが沈静化し、緊急事態宣言が解除されたことで、街中の人出は増えており、景気は回復している模様だ。12月の月例経済報告は「このところ持ち直し...
-
2021/12/24初心者が見るべき日銀短観のポイントを解説 –客員エコノミスト 〜塚崎公義 教授 –■日銀短観は大規模なアンケート ■市場関係者の関心が高いので株価に影響 ■景気予想屋は幅広い項目をじっくり見る ■アンケートの癖には要注意 (本文) 先日、日銀短観が発表された。内容を見ると、総じて言えば景気の回復を示すものとなっているので、投資家は安堵したのではなかろうか。内容については別の機会に論じるとして、今回は日銀短観というものについての初...